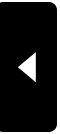2012年03月11日
共喰い
芥川賞作の共喰いを読んだ。
文章は決して読みやすいほうではなく、物語を引っ張るストーリーも弱いために、読み進めるのがいくらか苦労した。
あらすじとしては、遠馬という主人公とその父、そして彼の彼女、生みの親と、現在の後妻。
の面々の織り成す日々。性と暴力。
中上健次の岬、枯木灘か。選者も触れていたが。
父親殺しという、重苦しく、暗いテーマを扱っているにもかかわらず、結末に、主人公らが笑みさえ浮かべているかのような感じになるのは、どういうわけであろうか。
文章は決して読みやすいほうではなく、物語を引っ張るストーリーも弱いために、読み進めるのがいくらか苦労した。
あらすじとしては、遠馬という主人公とその父、そして彼の彼女、生みの親と、現在の後妻。
の面々の織り成す日々。性と暴力。
中上健次の岬、枯木灘か。選者も触れていたが。
父親殺しという、重苦しく、暗いテーマを扱っているにもかかわらず、結末に、主人公らが笑みさえ浮かべているかのような感じになるのは、どういうわけであろうか。
Posted by なみログ at 17:51
2012年03月07日
眉山(太宰治)
 | グッド・バイ (新潮文庫)著作者:太宰 治 出版社:新潮社 価 格:540 円 |
2002年9月に書いた独読日記から再掲。
『眉山(太宰治)』※グッド・バイに収録されている。
眉山とあだ名をつけられた飲み屋の女中。主人公である僕たちが飲み屋に行く度に、彼女はかいがいしく彼らの世話をするが、彼たちが呼びもしないのに、彼らの輪の中に入り、いつのまにか話しに加わってしまうことや、どこかピントのずれたその様子に、僕たちは彼女を嘲りの目でも見つめている。
物語の終り、久しぶりに飲み屋にいったというある人物と僕は出会い、眉山がいないことを聞かされるが、眉山が腎臓結核を患っていたこと、彼女がかいがいしく振舞う姿にどこかぎこちなさを感じたり、おしっこをもらしたことがあったということなどが、全て腎臓結核のせいであったということを知らされる。
短くて、本当にあった話を下敷きに書かれていると思う小説だが、文章のうまさもさることながら、最後になって眉山の病気の真相が伝えられたときの僕の心象など、さらっとした表現のなかにも胸を打つものがある。
2012年03月05日
蛇を踏む(川上弘美)
2002年12月に書いた独読日記より再掲。
現在旬の作家の小説を題材にしようということで、「蛇を踏む」を読書会で取り上げた。読書会の主旨に「たまには小説を読み込んでみよう」というのがあり、「読み込む」ことなしには会が成立しないのだが、果たしてどう「読み込めるか」。読み手が試されているような作品である。小説は必ずしも「読み込む」ことが必要かどうかという問いも含めて。
主人公のサナダさんは数珠屋さんの店番をする女性で独り暮らし、彼女の家に母と名乗る「蛇」が突然居座ることになるのだが。。
「蛇の世界は暖かいわよ〜」と蛇はサナダさんを自分の世界に引き込もうとするが、彼女は「蛇の世界」に惹き付けられるところもみせるが、拒絶感も抱いている。結局「蛇の世界なんてないのよ」ときっぱりと断言するのだが、「蛇の世界」とは一体何であろうか。
僕は「蛇の世界」というのは、もっと人(ここでは蛇も)と人が密接に付き合って生きていくような世界だと解釈し、「蛇の世界」ではないサナダさん自身のこれまでの生き方は、人づきあいについて距離感を保とうとしてきた生き方ではなかったかと思う。そういう自分を肯定して生きてきたが、だがもっと周りの人たちのように、べったりとした人と密接に触れ合っていくような、そんな自分になりたいとも思っている。
現代人の対人関係の距離感を描いているのかと。
「蛇の世界」に行くのか、「今の世界」にとどまるのか、といっちゃうと、ずっと以前のこの日記にも書いた(※ずっと下を参照)、村上春樹の「世界の終りとハードボイルドワンダーランド」のパロディかということになるが(笑)、この作品の押しの弱さをあえてあげるとすれば、「蛇の世界」とそれに対する「今の世界」の、双方の提示の仕方に深みがないかなーと思う。ただ作者がそこまで考えて書いているかどうかは疑問。
ところでこの作品の中に出てくる蛇について読書会の参加者は、リアルな蛇を思い浮かべるということだったが、僕は「水玉模様やパステルカラー」の蛇をイメージした。怖くなんて全然ないと(笑)。作者のイメージは僕に近いんじゃないかと思うんだが。違うかなー。
 | 蛇を踏む (文春文庫)著作者:川上 弘美 出版社:文藝春秋 価 格:440 円 |
現在旬の作家の小説を題材にしようということで、「蛇を踏む」を読書会で取り上げた。読書会の主旨に「たまには小説を読み込んでみよう」というのがあり、「読み込む」ことなしには会が成立しないのだが、果たしてどう「読み込めるか」。読み手が試されているような作品である。小説は必ずしも「読み込む」ことが必要かどうかという問いも含めて。
主人公のサナダさんは数珠屋さんの店番をする女性で独り暮らし、彼女の家に母と名乗る「蛇」が突然居座ることになるのだが。。
「蛇の世界は暖かいわよ〜」と蛇はサナダさんを自分の世界に引き込もうとするが、彼女は「蛇の世界」に惹き付けられるところもみせるが、拒絶感も抱いている。結局「蛇の世界なんてないのよ」ときっぱりと断言するのだが、「蛇の世界」とは一体何であろうか。
僕は「蛇の世界」というのは、もっと人(ここでは蛇も)と人が密接に付き合って生きていくような世界だと解釈し、「蛇の世界」ではないサナダさん自身のこれまでの生き方は、人づきあいについて距離感を保とうとしてきた生き方ではなかったかと思う。そういう自分を肯定して生きてきたが、だがもっと周りの人たちのように、べったりとした人と密接に触れ合っていくような、そんな自分になりたいとも思っている。
現代人の対人関係の距離感を描いているのかと。
「蛇の世界」に行くのか、「今の世界」にとどまるのか、といっちゃうと、ずっと以前のこの日記にも書いた(※ずっと下を参照)、村上春樹の「世界の終りとハードボイルドワンダーランド」のパロディかということになるが(笑)、この作品の押しの弱さをあえてあげるとすれば、「蛇の世界」とそれに対する「今の世界」の、双方の提示の仕方に深みがないかなーと思う。ただ作者がそこまで考えて書いているかどうかは疑問。
ところでこの作品の中に出てくる蛇について読書会の参加者は、リアルな蛇を思い浮かべるということだったが、僕は「水玉模様やパステルカラー」の蛇をイメージした。怖くなんて全然ないと(笑)。作者のイメージは僕に近いんじゃないかと思うんだが。違うかなー。
2012年02月25日
13階段(高野和明)
 | 13階段 (講談社文庫)著作者:高野 和明 出版社:講談社 価 格:680 円 |
47回江戸川乱歩賞受賞作品。
ずいぶん前に買っていて、どこに行ったかわからなくなっていた本書が、無造作に詰まれた本の中から見つかったので、読み始めた。
話の筋はとても面白そうだ。はてさて、どのような展開なるのか。
文庫版の解説に宮部みゆきさんが書いていて、映画の評価があまり芳しくなかったと書いてある。映画も気が向けばDVDで見てみようかと思う。
※話はそれるが、宮部みゆきさん原作の『模倣犯』の映画は??だった・・
※話はそれるが、車谷長吉さん原作の『赤目四十八瀧心中未遂』の映画も??だった・・
2012年02月20日
文学読書会in八王子高尾
なみログの独読日記をご覧の皆さま、こんにちは。
昨日は、八王子高尾駅近くの<プラザむみじか>(高尾駅南口徒歩3分/八王子市初沢町1299)で開催された、つながりまつりで読書に関する講演を行った。
イベント自体は11時から開催されていて、11時からすでに20名以上の方が会場に入って、午前中のプレゼンテーションを熱心に聴いていた。
13時から始まった僕の講演は、10名の方にそれぞれ5名ずつ二つの机についてもらい、あと立ち見でも10名程度の方に聴いてもらった。
講演のテーマは、『読書で地域が活性化できる!』。
果たして、本当に読書で地域が活性化できるのかどうか、聴く者皆ばかりか僕自身でさえも半信半疑のスタートであった・・

ここから約10分。あーだこーだ、読書に関する僕なりの話をし、
次に、具体的に読書を参加者みんなで実践してみましょう。
ということで、昨日は時間の関係上、小説ではなく、童謡の『ふるさと』の歌詞をみんなに配り、
ふるさとの歌詞に5分間向き合ってもらった。
静かに詞に向き合う。
ことが大切だ。
そして、5分の黙読が終わり、5名ずつのグループで自己紹介を行い、感想をシェア。
黙読のときからであったが、おもわず泪を流される方、感想をシェアするともらい泣きする方がいらした。
どのような想いが胸の内に去来したかは、話の詳細が聞こえなかったので、分からないが、
約10分くらいそれぞれの立場でそれぞれの<ふるさと考>を語り合ってもらった。
そうして簡単ではあるが、読書体験を地域の仲間で語り合うということの実際を体験してもらった。
読書会は、
読書という体験をとおして語られる、お互いの人生や考え方、地域のことなどについて、
世代を超え、性別を超え、他人の思いを知り、その土地の風土や歴史、生活を知り、
そしてそこから
自分自身の生き方につなげていく、
ことに目的がある。
何冊もの小説のタイトルを知っているかとか、小説のあらすじを知っていることなどももちろん読書体験の成果であり喜びであるかもしれないが、
読書会で得られる読書体験の効能は、小説の物語の世界を飛び越えて、人生の生きるヒントを得られるところにある。
読書を通して地域で人が集い語り合うことで、人生をよりよくしよう、地域をよりよくしようという気運が生まれ、仲間意識が強まり、そこから次はなにか行動に移すことが生まれるだろう。
講演の最後、『読書で地域は活性化すると思いましたか?』という問いに、
参加者のみんなが賛成の手を上げてくれた。(ちょっと強引?・・(笑))
■過去の読書会イベントの様子
大人の文学読書会in佐賀県(2011年11月)
◆◇◆◇文学読書会や読書啓発の講演依頼はお気軽に♪♪◆◇◆◇
オーナーにメッセージからお問い合わせください。
昨日は、八王子高尾駅近くの<プラザむみじか>(高尾駅南口徒歩3分/八王子市初沢町1299)で開催された、つながりまつりで読書に関する講演を行った。
イベント自体は11時から開催されていて、11時からすでに20名以上の方が会場に入って、午前中のプレゼンテーションを熱心に聴いていた。
13時から始まった僕の講演は、10名の方にそれぞれ5名ずつ二つの机についてもらい、あと立ち見でも10名程度の方に聴いてもらった。
講演のテーマは、『読書で地域が活性化できる!』。
果たして、本当に読書で地域が活性化できるのかどうか、聴く者皆ばかりか僕自身でさえも半信半疑のスタートであった・・

ここから約10分。あーだこーだ、読書に関する僕なりの話をし、
次に、具体的に読書を参加者みんなで実践してみましょう。
ということで、昨日は時間の関係上、小説ではなく、童謡の『ふるさと』の歌詞をみんなに配り、
ふるさとの歌詞に5分間向き合ってもらった。
静かに詞に向き合う。
ことが大切だ。
そして、5分の黙読が終わり、5名ずつのグループで自己紹介を行い、感想をシェア。
黙読のときからであったが、おもわず泪を流される方、感想をシェアするともらい泣きする方がいらした。
どのような想いが胸の内に去来したかは、話の詳細が聞こえなかったので、分からないが、
約10分くらいそれぞれの立場でそれぞれの<ふるさと考>を語り合ってもらった。
そうして簡単ではあるが、読書体験を地域の仲間で語り合うということの実際を体験してもらった。
読書会は、
読書という体験をとおして語られる、お互いの人生や考え方、地域のことなどについて、
世代を超え、性別を超え、他人の思いを知り、その土地の風土や歴史、生活を知り、
そしてそこから
自分自身の生き方につなげていく、
ことに目的がある。
何冊もの小説のタイトルを知っているかとか、小説のあらすじを知っていることなどももちろん読書体験の成果であり喜びであるかもしれないが、
読書会で得られる読書体験の効能は、小説の物語の世界を飛び越えて、人生の生きるヒントを得られるところにある。
読書を通して地域で人が集い語り合うことで、人生をよりよくしよう、地域をよりよくしようという気運が生まれ、仲間意識が強まり、そこから次はなにか行動に移すことが生まれるだろう。
講演の最後、『読書で地域は活性化すると思いましたか?』という問いに、
参加者のみんなが賛成の手を上げてくれた。(ちょっと強引?・・(笑))
■過去の読書会イベントの様子
大人の文学読書会in佐賀県(2011年11月)
◆◇◆◇文学読書会や読書啓発の講演依頼はお気軽に♪♪◆◇◆◇
オーナーにメッセージからお問い合わせください。
2012年02月19日
2012年02月17日
謎とき『カラマーゾフの兄弟』(江川卓)
 | 謎とき『カラマーゾフの兄弟』 (新潮選書)著作者:江川 卓 出版社:新潮社 価 格:1,365 円 |
先週、久しぶりにドストエフスキーの世界に戻った。
カラマーゾフの兄弟を読み進める中で、スメルジャコフのことが気にかかって仕方がなかったが、江川氏もまたスメルジャコフが気になっていたことが判明し、かれを知ることがカラマーゾフの兄弟をさらに知ることにつながるのだろう、という推測は当たっていた。
果たして、スメルジャコフとは何者として描かれたのか?
そして実際に何者だったのか?
<実際に>という言い方はフィクションに向う言葉としてはふさわしくないが、作者の<企図>としていたスメルジャコフが、<実際に>物語の中で作者の<企図>を離れてしまうことはなかったか?
スメルジャコフのあの陰鬱な雰囲気。やけに論理的な会話。イワンに対する愛憎とも受け取れる忠誠と裏切り(?)
カラマーゾフの兄弟を深く知るための手がかりとして、スメルジャコフのことをもう少し考えてみたい。
カラマーゾフの血が流れているのは、ドミートリー(長兄)、イワン(二男)、アリョーシャ(三男)。三人の兄弟だけではない。スメルジャコフにもカラマーゾフの血が流れているわけであるから。
2012年02月11日
たかされ(本宮ひろ志)
 | 実録たかされ 2 (BiNGO COMICS)著作者:本宮 ひろ志 出版社:文藝春秋 価 格:530 円 |
理由が分からないが、父親が江川卓さんのファンで、江川さんが投げるときはテレビの野球中継観ながら、父親があーだこーだうんちくを披露していた思い出がある。
江川が投げるときは、早く終わるから弁当が売れないとか、球が調子のいいときは、バットが下を空振りするとか、9回でも140キロなげるとか。
その後、うるぐすでスポーツキャスターしてるときや、テレビの野球解説者のときも、良く観てたので、よっぽど好きなのだろう。
ということもあってか、僕も江川さんは好きだが、あまり現役時代は覚えていない。高校時代がピークだったといわれるし、また、アメリカ浪人中にはメジャーリーグからも話があったというから、若いときの投球を見てみたかった。
Posted by なみログ at 07:52
2012年02月06日
文学と情報知識
 | 超・殺人事件―推理作家の苦悩 (新潮文庫)著作者:東野 圭吾 出版社:新潮社 価 格:460 円 |
東野圭吾氏の、本書。
タイトルおよび表紙から得られる印象と違い、いくつかの話は、とても考えさせるものだった。
とくに最後の、超読書機械殺人事件と、超長編小説殺人事件
この二つは深い。
超読書機械殺人事件は、まさに今のネットに転がる一部の批評文(あらすじ、要約文も)とそれを見る読者を予言したかのような内容。
ショヒョックスなる、書評作成機械を販売するセールスマン。そしてそれを購入する書評家たち。
※あらすじ抽出機能や、要約機能はショヒョックスの基本機能として装備されている。さらに書評まで機械がしてくれるという。
※こうやって書評ブログなるものを書いている僕自身も、素人とはいえ、東野圭吾氏が指摘する書評家たちの一人であるのか。
ひとたびショヒョックスに小説を読み込ませると、辛口やヨイショなど書評の味があり、それを選択するとその味の書評が出来上がるというもの。
ショヒョックスの次は、物語を作る創作用の機械が出てきて、そこには物語を実作する人間も、実際に本を読んで書評を書く人間もいなくなるという話。
おー怖。
それから、超長編小説殺人事件も、興味深い。中でも興味深いなあと思ったのは、小説の内容に、情報小説という、読者が詳しく知らない業界の話や裏話を盛り込み、情報をほしがっている読者向けに、小説を水増しするというもの。あまりその部分が長すぎると、小説の筋とはかけ離れているので間延びした形になるが、それでも読者がそのような情報小説部分を望んでいるというニーズもあるということ。
いやいや、これは凄い話だ。確かに、主に経済小説やミステリーはそのような情報小説的な要素が多く入ることの余地のあるジャンルだろうが、そういうことが一つのテクニックとして確立しているというのは。もちろんなんとなくは知っていたし、業界ネタを書くといいという新人賞獲得のノウハウ本もあったが。
文学と情報知識は、ある意味全く関係の無いことのように感じるが、どんどん文学が情報知識芸術化しているような印象を持つ。※そうなると果たして芸術なのかという問題も出てくる。小説=情報知識コンテンツという言い方が妥当か。
文学作品は、もちろん情報知識コンテンツではないのだけれどね。
たとえば、もしドラなんかも、情報小説だろう。(ということであれば映画は失敗すべくして失敗したということになる。)情報はインターネットやビジネス書で読めばいい話で、映画で見るものではないのだから。
そもそもあらすじや要約を知っていることと文学作品を読んだこととは何の関係性もあるはずはなく、ましてや、文学作品を読むということは、少なからず生き方や考え方になんらかしらの作用が働くものであり、ときに文学作品は読者の生き方により良いヒントを与えるものである。
2012年01月30日
映画砂の器(野村芳太郎監督、松本清張原作)

映画砂の器を観た。
ずいぶん前にテレビ放送で観たような観ていないような記憶だったので、改めて見直した。
原作より良いと感じる映画は、よく言われるようにほとんど無いけれど、砂の器は原作以上に映画が良いと感じた。
まず、原作のさまざまな登場人物を絞り込んで、父と子、今西刑事と同僚の刑事の4人に絞り込んでいるところ。(あとは女性二人が目立つくらい)
それにともない思い切って、筋を変えているところ。
それから、一番の素晴らしい演出は、宿命の音楽に乗せて、父と子の放浪の物語部分を映像化して見せたこと。
とまあ、よく言われる感想が挙げられる。
筋以外でも、映像美が素晴らしく、日本の四季を各地で撮って映像化している。地方の駅や野山、川、岸壁、村、など日本の自然風景が撮られている。
これは、映画が公開されてから四十年近く経った現代においては、ますます、貴重な映像になったのではないだろうか。
水上勉氏の『飢餓海峡』は小説は砂の器より面白いと思うが、映画がつまらなく思えたのは、原作にほぼ沿った形で物語が流れたからかもしれない。飢餓海峡ももっと絞り込んで描いていればと思わせる。どうだろうか。もちろんそれで十分取捨選択されていての結果だと思うし、恐山の捉え方などは映画の演出なのだが。
2012年01月23日
八王子<つながりまつり>で読書講演!!
2月19日(日)八王子高尾駅南口、プラザむみじかで行われる<つながりまつり>(東日本大震災復興チャリティイベント)に、読書に関する講演を行うことが決定しました!
講演のお題は<読書で地域を活性化ができる!>です。
私の講演は、13時からとなっています。
お近くの方や興味のある方はぜひ当日会場まで足を運んでください。
※つながりまつりの売上の一部を、東日本大震災の被災地・避難者支援、
動物の命を守る活動支援のために寄付させて頂きます。
【主催】つながりまつり実行委員会
【共催】たまりば運営事務局、つながろう!八王子で!
【協力】磯沼牧場、ルクツン八王子、ぬくもり工房 京昌、北鹿(秋田県の地酒)、
福島原発動物本気で守る会HOSHI FAMILY
【入場料】500円(1ドリンクサービス付き)?※未就学児は無料
【日時】2012?2月19日(日) 11:00?18:00(開場10:45)
【会場】プラザむみじか(高尾駅南口徒歩3分/八王子市初沢町1299)
■詳しくは下記のサイトをご覧ください。
http://tsunagari.tamaliver.jp/
2012年01月23日
レディ・ジョーカー DVD観た。
レディ・ジョーカーのDVD を借りてきて観た。
やっぱり、そうかと思ってしまうほかないが、筋を伝えるためにどうしても、エピソードがかいつまんだ格好になってしまい、薄っぺらさが否めなかった。難しいと思うし。
何故レディジョーカーという名前であるのか?
という問いと答えはなかったなあ。
レディがモチーフと動機に少なからずなっているはずなのに、それがまるっきり触れらずじまい。
合田と半田の対決もなにか時間に迫られたように、あっけない。
あっけないのはまだ判るが、そこにいたるまでの、半田の追い詰められていく様と、合田が狂っていく様をもう少し描いて欲しかった。
吉川晃二が、素晴らしい演技をしていただけに、
やっぱり、そうかと思ってしまうほかないが、筋を伝えるためにどうしても、エピソードがかいつまんだ格好になってしまい、薄っぺらさが否めなかった。難しいと思うし。
何故レディジョーカーという名前であるのか?
という問いと答えはなかったなあ。
レディがモチーフと動機に少なからずなっているはずなのに、それがまるっきり触れらずじまい。
合田と半田の対決もなにか時間に迫られたように、あっけない。
あっけないのはまだ判るが、そこにいたるまでの、半田の追い詰められていく様と、合田が狂っていく様をもう少し描いて欲しかった。
吉川晃二が、素晴らしい演技をしていただけに、
2012年01月20日
俺のレディ・ジョーカーはまだ終わっていない。
半田が物井に言う科白だ。
あんたらには関係ない。俺個人の問題だ。
府中競馬場で、後ろ姿を眺める半田に、物井がいう。
知っているのか?
半田はいう。
刑事だ。俺に惚れているのさ。
言わせるやん。
映画では半田役を吉川晃二がしていて、いいらしい!!
あんたらには関係ない。俺個人の問題だ。
府中競馬場で、後ろ姿を眺める半田に、物井がいう。
知っているのか?
半田はいう。
刑事だ。俺に惚れているのさ。
言わせるやん。
映画では半田役を吉川晃二がしていて、いいらしい!!
Posted by なみログ at 00:16
2012年01月17日
レディ・ジョーカー(高村薫)
レディ・ジョーカー。
タイトルがいい。脅迫事件を起こす一味たちの名前だ。物語の中に、レディジョーカーに命名するモチーフがあり、読んでいる側もすごく納得することができた。
脅迫される側の日之出ビールの城山社長や刑事の合田には、なぜレディジョーカーなのかまったくわからなかっただろう。事情の分からないものには全く分からない、名前だ。しかし、命名に加わった仲間たちにとって、レディジョーカーという名前は、あとから考えてもこれしかなかったのではないかと思えるほど、かれらの立場をよく物語ってはいないだろうか。
レディジョーカーたちのやった犯罪や彼らの姿や行動が、凶悪なものとは無縁と感じるばかりか、物井の正体がいつばれないかハラハラしたり、合田からつけ狙われる半田に、肩入れしたりする気持ちが湧くのはなぜであろうか。
とくに半田。あんたが抱えているものがなんだったのか、それはたいそう重いものだったのか、それとも、実のところはそうでもなかったのか。
2012年01月12日
照柿(高村薫)
 | 照柿(上) (講談社文庫)著作者:高村 薫 出版社:講談社 価 格:680 円 |
さて、照柿。
ミステリと予断をもって読む始めると、ちょっと頭が混乱するかもしれない。
広義のミステリという範囲の、<広義>の部分に属する作品なのだろう、と個人的には思うことにした。
合田という刑事と、野田達夫という幼馴染の男と、二人の間に存在する女の話が全てであり、その話の合間に事件の話があるというバランスか。
タイトルの照柿。
合間合間に、なんどもその色について描写があったり、説明があったりするが、なんかしっくりと照柿というタイトルにもしたモチーフの大きさが伝わってこない。
作品のなかにあり、照柿の占める大事さというのが伝わらなかった。
※先に照柿色ありきなのかもしれないなあと思ったりした。
青い鴉。
というタイトルではダメだったのか?
達夫の人生において青い鴉の挿話は、インパクトがあるし、合田と彼の関係のすべては青い鴉の事件が、かれの所業の数々の動機の根源ではなかったか。
照柿の合田刑事は、この後所轄に転属願いを出し、レディ・ジョーカーで再び作品に戻ってきたが、照柿を読めば、レディ・ジョーカーで徐々に狂い始める彼のことが判らないではないが、マークスの山の合田刑事と、照柿の合田刑事は、あまりにも違う人物に変わってしまっているようで、その間をつなぐエピソードがないものだろうか。短編小説とかで書かれているのかな。
2012年01月10日
マークスの山(高村薫)
 | マークスの山(上) (講談社文庫)著作者:高村 薫 出版社:講談社 価 格:680 円 |
なみログの独読日記をご覧のみなさん。今年もよろしくお願いします!
年末年始にぼちぼちと高村薫氏の著作を読んだ。
レディ・ジョーカー
マークスの山
照柿
レディ・ジョーカーの下巻の途中で、合田雄一郎刑事(警部補)を最初から読まねばならぬな、と内心思っていたら、ほんファンブロガーさんのご助言もあったので、マークスの山を読むことにした。
マークスの山。
映画がテレビ放映されたときに見た記憶があり、映画は面白かった印象がある。
話の筋もすべて忘れていたので、新鮮に読んだ。
レディ・ジョーカーで、半田刑事から狙われることになる合田雄一郎という男。マークスの山での登場はイメージよりちょっと遅く。そして、それほど人物が掘り下げて描かれているわけではない。颯爽とした感じのある刑事像で、合田刑事だけではなく、林、吾妻、森、又三郎などの捜査一課の面々、刑事群像の中の一人として登場している。
ということで、マークスの山では合田は、とある刑事の一人であり、あくまで事件と合田の人生や業、宿命といった関わりはそんなに深くは無い。
さて、マークスの山の本題だが、マークスを名乗る連続殺人鬼の水沢は、多重人格者で、裏の人格であるマークスが水沢を操り、殺人を犯す。
話自体はよく考えられたものであるが、そもそも、マークスがかれに宿ることになった原因である、山でのMARKSたちの殺人事件との遭遇の箇所が書かれていないので、なにかはがゆい気がした。
都内から逃げてそのまま北岳の山頂で死んでいたというラスト。もう一悶着か二悶着、あってもよかったのかもしれないなあと。
一転して照柿は、合田刑事の境遇や内面を粘っこく描いていて、こちらは事件うんぬんは案外さっぱりしているのに、なぜかじっとりとしたものになっている。照柿の感想はこの次に。
2011年12月29日
佐賀ラーメンとレディ・ジョーカー
高村薫氏のレディジョーカーは今日深夜ホテルで中巻を読了。
誤認逮捕という失態に合田刑事がどう挑むのか?半田警官を含むレディジョーカーの現金授受は成功するのかどうか?
ちょっと興奮した状態で読んでます。
全く事前情報を知らない状態で読んでいるので、どういう展開になるのか。目が話せない感じになってます。
いよいよ下巻に突入です!
写真は佐賀の豚骨ラーメンです。
博多や長浜、久留米とも違い、佐賀ラーメンというくくりのラーメンです。
東京で佐賀ラーメンはなかなか食べれないので大満足でした!
Posted by なみログ at 09:34
2011年12月25日
レディ・ジョーカー(高村薫)
遅れて読み始めたレディ・ジョーカーの上巻を読み終えた。
照柿にくらべると、読みづらいと思っていた主人公の心象描写が適度に抑えられているようで、ずいぶん読みやすくなっている。
かといって、小説の品質が落ちるのではなく、評判どおり、物語、登場人物のキャラクター、舞台装置、文体、ディテールなど、およそ小説の構成に必要なものが高いレベルで書かれている。
競馬場のシーンもよく描かれているなあと関心しきり。
年末は高村薫氏を読むことに決めた。
2011年12月21日
照柿(高村薫)
随分前から買っていた照柿。
何度も読み始めたことはあったが、話になかなか引き込まれず、読み進めるのを諦めた。
面白いという評価が多いので、間違いなく面白いのだろう。
ミステリーにしては話の筋より主人公の合田という刑事と、達夫という幼なじみの心象描写が多く、文章も手連なだけに読ませる。が、やや饒舌か。
2011年12月19日
郵便配達は二度ベルをならす(ジェームスケイン)
 | 郵便配達夫はいつも二度ベルを鳴らす (ハヤカワ・ミステリ文庫 77-1)著作者:ジェイムズ M.ケイン 出版社:早川書房 価 格:546 円 |
カミュの「異邦人」の下敷きにもなっているという話を教えていただき、本作を探した。町の本屋さんにはなく、ネットで買うことになった。
主人公のフランクチェンバーズ。「異邦人」のムルソーより少し身近に感じたのだが、「異邦人」を読んでから少し時が経ったからだろうか。カミュへの影響もあるかもしれないと思ったが、アラン シリトーはどうだろうか?と思った。シリトーの「土曜の夜と日曜の朝」などは、結構感じが似ていると思ったのだが。
この作品は映画でも有名なのだが、見たことがなかったので、ぐいぐいと引き込まれるように読み進めた。
女とともに女の夫を殺すという完全犯罪を企みに成功し、二人は上手いこと執行猶予で逃れることができるのだが、彼ら二人が得たものと失ったもの。結末にある突然の悲劇に読むものは一瞬にして悲しみのどん底へ突き落とされる。殺人を犯したものたちの悲劇に対してなぜ悲しんでしまうのか。「異邦人」の「ムルソー」もそうであるが、彼が犯した罪と罰。彼の置かれた環境と立場。彼が得たものと失ったもの。そういうものを一つずつ整理して考えてみる必要があると思わせる作品だった。
それから、映画はどうなんだろうかと思う。