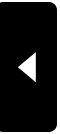2011年10月16日
2011年10月16日
2011年10月15日
2011年10月13日
スタヴローギンの告白
悪霊の、ニコライスタヴローギン外伝にあたる章を読んだ。
息をつかせぬ文章、設定舞台である。
チホンとスタヴローギンの会話の応酬は全てを理解はできないが緊迫感があって、読みごたえがあった。
息をつかせぬ文章、設定舞台である。
チホンとスタヴローギンの会話の応酬は全てを理解はできないが緊迫感があって、読みごたえがあった。
2011年10月13日
悪霊 読了
深夜眠れずに、3時半頃から起きて、悪霊を読む。
読了。
※ニコライ・スタブローギンの告白の章が最後についていたが、そこはまだ。
ピョートルの陰謀によるシャートフ殺しと、キリーロフの自殺のくだりにいたっては、さすがにぐいぐいと読ませた。
また、奇怪な事件後のステパン氏が放浪の旅に出立し、病気になり、ワルワーラ婦人が迎えに来る話のところは、メロドラマ風であることは否めないが、感動が盛り上がってきた。
ニコライと、ピョートルの関係性や、ピョートルが組織化しようと画策した混乱の絵図については、少し詳しく別の投稿で書きたいと思う。
改めて思ったが、ドストエフスキーは面白い!
2011年10月12日
太市 (水上勉)

この短編アンソロジーの中に収録されている、水上勉の「太市」。
これは、一読をおすすめする。これまでも、多くの価値感を脅かされる文学作品に出会ってきたが、この短い物語の中に、何ともいえないせつないというか、もの悲しさと、また、怖ろしさを感じる。
車谷長吉氏と水上勉氏の対談が掲載してある本のなかに、車谷氏が「太市」を読んで凄い小説だと思ったということを告白しているのだが、まさにそのとおりだなと思わせる作品だ。
多くの人に「太市」を読んでもらいたいと思う。
似たような感慨を抱いた小説に、イギリスの作家アラン・シリトーの「フランキー・ブラーの没落」という短編がある。フランキー・ブラーの没落を何度も読んでいたからこそ、太市の話が、予定調和的に悲しみを誘発したのかもしれない。
2011年10月11日
月と蟹 (道尾秀介)

〜2011年1月のノートより〜
直木賞受賞作、月と蟹を読んだ。
小学五年生が主人公のわりに、心理描写や地の文が大人すぎて違和感を少しは感じるが、文章も巧みで、ストーリーもよかった。
タイトルの月と蟹、子どもたちが崇め立てるのはヤドカリで、月と蟹というタイトルより、ヤドカリに引っ掛けた別のタイトルでもよかったか。
もっと短くて、100枚〜150枚くらいの短編だったらどうだろうと思ったりもする。
宮本輝の短編のように。
いや、そんなに宮本輝を読んでいるわけではありません。(汗)
2011年10月10日
2011年10月10日
2011年10月08日
哀しい予感 (吉本ばなな)

〜2003年6月のノートより〜
読書会で取り上げた。
彼女の書く初期の小説は、感性がみずみずしく、ノスタルジックな印象を与える。読書会に出席した60代の女性は、「哀しい予感」をとても面白く読んだと言われ、この歳になると気持ちがみずみずしいものを受け入れるようになるのかな、と言われた。そんな風に年齢差を超えて親しまれる作品をうらやましいとさえ思う。
さて僕の感想だが、ストーリー展開に唐突感があった。急なドラマを見せられているような感じ。おばを探しに青森まで行くのだが、あっけなく姉が見つかってしまう。あまりにも偶然すぎて、現実味に欠ける。そういう意味では前半が面白いし、登場人物の個性がよく描けている。おばの人物設定はとても効いている。
「哀しい予感」とは何に対する予感なのだろうか。弥生が自己を確立するために、避けてはとおれない「家族の解体」。その哀しさを予感するものだろう。たしかに家族は解体するのだろうが、この小説の後味の良さは、そこに光があるからだ。育ての両親の弥生に対する深い思いや、彼等に対する弥生の素直な気持ち。暗さはない。
ただ、物語の底を流れる哀しさ、残酷さ。僕はそこを考えていたのだが、物語を巡って一つの解釈をしてみたい。それは両親が死ぬことになった青森の最後の旅行は、そもそも一家心中をする目的ではなかっただろうか、という解釈だ。一家心中のために向かった旅行の途中で、不慮の事故に遭遇し、両親は亡くなる。残されたのは姉と妹。妹は血のつながりもなにもない夫婦に預けられ、事故のショックから本当の両親のことについては何も覚えていない。姉はそれまでの生活環境を変えることができないという理由から、一人で暮らすことを選択するが、その裏に隠された思いは、両親と一緒に死ぬことができなかったことに対する複雑な思いが、彼女を一人にさせたのではないだろうか。
ひねくって考えすぎているかも知れないが、そういう感じがいたるところにする作品である。
2011年10月07日
闇の奥 読了
地獄、地獄だ!
アフリカの奥地で重篤な病のために捕らえられ護送されるクルツという象牙商人の最期の言葉である。
かれはジャングルの中で原住民たちから偶像崇拝されモラルと人間性の破綻した暴虐のかぎりをつくしていたのだが、大地奥深く人知の知れぬ闇黒の中で、原始欲望になかばかれ自身さえも征服されてしまう世界というか、小説のなかでは荒野とかかれているが、そのような荒野において、果たして、われわれが世界だと思い過ごしている世界とはなんなのだろうかという問いをいだかずにはいられない。いったいわれわれがあたりまえにみにつけている人間性とはなんなのだろうかと。
1899年に書かれたこの物語の語り手であるマーロウは、闇の奥からの帰還後に見たフランスパリの墓場のような都会に、強い嫌悪感を抱く。互いに零細な金をくすね合い、くだらない、愚かな夢を見ている群集にだ。
地獄、地獄だ!
と吐き捨てられた言葉の先にあったのは、果たしてアフリカの闇の奥のことだったのか、文明都市のことだったのか。
コンラッドがクルツに吐かせたときから、もう100年以上が経つ。
◆闇の奥に関して書かれたサイト
闇の奥(ウィキペディア)
地獄の黙示録(ウィキペディア)
『闇の奥』の奥(藤永茂著)
「『闇の奥』の奥」について書かれたサイト
http://www5b.biglobe.ne.jp/~madison/mondo/m_04/m04_1.html
2011年10月06日
闇の奥 (コンラッド)
コッポラは時代背景と舞台をベトナム戦争の泥沼化した時代に移した。
小説の闇の奥はアフリカの奥地を舞台に文明の衝突、原住民迫害、狂気を描く。ちょっと読み始めただけでも、息を飲み、顔をしかめたい情景描写が続く。
はたしてこの小説は、何が語られ、どのようにして終わるのか。
2011年10月05日
裸の王様 (開高健)

〜2008年のノートより〜
※ネタばれ注意!!!オチを書いています!!!
家のパソコンの横に本棚があり、開高健の裸の王様の文庫が目にとまった。
パラパラとしてみる。
赤ペンで書き込みが。
裸の王様と裸の王様の二重の仕掛け。
なんのことやらすぐには思い出せない。
あ、そうか、
裸の王様を題材に読書感想画を描かせたところ、ふんどしをしめたちょんまげ姿の裸の殿様を描いた少年が出てきたということと、
その少年の作品を見もせずにほかの作品を優秀賞にした審査員たちのふしあなを、見抜いたということ
二つの側面で、<裸の王様>がしかけられている。
オチがみごとに構成された小説だ。
でも、と思う。
小説にオチはかならず必要なのかと。
開高健のこの作品の完成度は相当高いと思う。
実際に読んでみてもらえばわかるが、実によく書かれている。
でも、と思う。
できすぎてやしないかと。
どこか道徳的であり、教科書的であり、解釈もわかるし、巧みだとは思うが、
それ以上の訴えてくるものがないような気がするのだ。
2011年10月03日
文学入門(桑原武夫)
かぞえると7年間も行っていて、合計50回以上になります。
なぜ文学読書会を開催していたのか?
いろいろと説明することはできますが長くなるので 読書会を開催してみようと思った一冊の本を紹介します。
桑原武夫氏の『文学入門』です。
1950年1月に書かれた本書には、『なぜ文学は人生に必要か』という問いにたいする解説があり アンナカレーニナの読書会を実際に行った模様を載せるなど、文学を読書することが有用なことについての、多くの示唆を与えてくれています。
2011年10月03日
白夜行(東野圭吾)

〜2007年のノートから〜
東野圭吾。
東野圭吾は面白い。
白夜行は最初読んだときに、ストーリー展開、行間に暗く潜む主人公二人の心理状態に、圧倒され、読み終わったときは少し放心状態のようになったものだった。
とうことで、冷静に二度目に挑戦。数時間で無事読了。
主人公である桐原亮司と唐沢雪穂。とくに雪穂の人物設定には関心する。二度目でとくに、雪穂の底知れない恐ろしさを知った。
亮司は、雪穂を守るために暗躍するが、最後は死ぬ。結果的に雪穂に操られただけではないか、といえないこともない。
ではなぜ?亮司ほどの頭脳明晰な男が、雪穂に操られているということに疑問を持たないはずはない。ということは、操られていないか、操られていても仕方の無い関係だったのか。
操られても仕方の無い関係だったとすると深読みになるので、やめるが、
亮司の心の闇は、雪穂以上のものがあるとさえ感じる。
 | 白夜行 (集英社文庫)著作者:東野 圭吾 出版社:集英社 価 格:1,050 円 |
.
2011年10月03日
砂の器(松本清張)
松本清張の『砂の器』上下巻を読了した。
映画を改めて見直してから、本編の感想は書きたいが、まずは小説の感想から。
ゼロの焦点を読んだあとに読んだ比較では、筋立ておよび文章、ともに砂の器が勝っていると思う。
砂の器というタイトルはものすごく文学的、芸術的であると感じるが、小説自体はあくまで推理小説であり、松本清張の試みも、それ以上のものはなかったのではないだろうか。
もちろん砂の器というタイトルが暗示するごとく、殺人を犯した犯人は、自らの名声、地位が砂で作った器のごとく、もろくも崩れ去るのだが、果たしてかれの人生は、他人が砂の器だと軽んじて非難してしまっていいようなものだったのかどうか。情状の余地があると、最後の説明の文章に何度かでてくるが、おそらく読む人にとって多少の印象の違いはあるにせよ、極悪犯には写らないのではないか。和賀という人物の様子は、小説の中では関川というもうひとりの容疑者よりも、人物像が薄くしか描かれておらず、和賀という人物の本当の、真実の言葉はどこにも書かれていない。果たして和賀という男はどのような人物だったのか、読む側に幾通りもの想像の余地を残した人物像である。
 | 砂の器〈上〉 (新潮文庫)著作者:松本 清張 出版社:新潮社 価 格:660 円 |